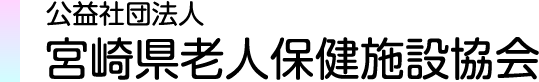4月29日は昭和の日です。1989年1月7日に幕を下ろした昭和。あれからもう四半世紀が過ぎてしまったとは・・・。64年という長きにわたっただけでなく、日本の歴史全体の中でも、重大な出来事がたくさんあった時代が昭和と言えるでしょう。四半世紀前に働き盛りだった40歳の人達は今、65歳になられるわけです。年号が平成に変わってから、時の流れが加速したかのような錯覚を覚えます。
そんな折、4月17日の日本経済新聞の1面に立った四段見出し。「65歳以上、3000万人突破」・・・。総務省が16日発表した2012年10月時点の推計人口によると、推計人口を出し始めた1950年以降、65歳以上の高齢者が初めて3000万人を越えたのだそうです。また、総人口にしめるその割合も24.1%と、過去最高になったとのこと。つまり昭和から平成に年号が変わった頃のアラフォー(当時はもちろんそんな用語はありませんでした)の方々が、高齢者の仲間入りをし始めたばかりでなく、全体としての高齢者も最多となったわけです。
「昭和は遠くなりにけり」と感慨にふけるばかりでなく、このような現状やこれから迎える新たな時代に向けて、老健施設に勤める者の1人としてどうするべきか?それを考える昭和の日にしたいと思います