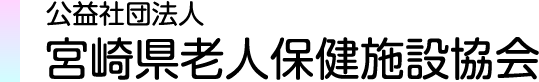研修会はまず講義「明日から始められるACP」がありました。講師は筑波大学医学医療系 緩和医療学・総合診療医学講師で、同大学附属病院 医療連携患者相談センター部長の医師、浜野 淳先生をお招きしました。浜野先生は数々の要職を歴任され、また人生会議(ACP)に関する講演活動で各地を飛び回るなど、多岐にわたって活動されています。この日はそんな激務の合間を縫って講師を引き受け、ご来県下さいました。ACPの第一人者である浜野先生の話が聞けるとあって、会場は開会前から熱気に包まれていました。

講義は「アドバンス・ケア・プランニング(ACPとは)」「人生会議とACP」「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(プロセス・ガイドライン)(意思決定する力とは?本人の意思決定とは?意思が確認できなくなることに備えた話し合い)」という流れで進められました。
「人生の最終段階の医療、ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に話し合うプロセス」というACPの定義(厚労省)にはじまり、「もしものときのために(特に自分で意思表示できなくなった時のために)、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組み」である「人生会議」などについて、豊富なスライドを使い、わかりやすい事例も交えながら講義が進められました。
その中で浜野先生は「ACPにおいて大切なこと」として、「人生の最終段階における医療・ケアについては、医師等の医療従事者から本人や家族等へ適切な情報の提供と説明がなされた上で、介護従事者を含む多専門職種からなる医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人の意思決定を基本として進める」ことを旨とする「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を示しながら、亡くなる場所の話ではなく、医療とケアのゴールについて話し合い続けること、心身の状態に応じて意思は変化しうるため、繰り返し話し合うことの重要性を強調しました。
(つづく)