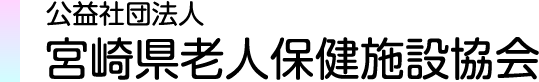さらに「意思決定する力」にも言及し、その評価を慎重に行うことやその際の注意点、「意思決定する力」を高める支援などについて触れつつ、認知機能が低下しているからといって、意思決定する力がないとは限らないことや、医療・介護従事者から見て適切ではない選択をしたからといって、「意思決定する力がない」と判断してはならず、本人の理解やこころの準備を無視し、医療・介護従事者からみて正しいと思われる選択を「あなたのためだから」を前提とした一方的な説得は「ありがちな失敗」と指摘。「特に『本人に良かれと思ってやっているとき』は、一方的な説得になっていることに気づきにくいです」と注意喚起しました。

その一方で、本人の意思の尊重だけを重視するのも、「医療、介護従事者が求められている医療者の考えをできていません」と指摘し、本人が必要とするときは、対話の中で医療、介護従事者の推奨を、理由を添えて伝えることが本人が決断をしやすくなると訴えました。
浜野先生の講義はさらに意思が確認できなくなることに備えた話し合いへと展開し、その具体的な進め方やポイントなどについて学びを深めました。ご多忙の中を縫って来県され、一人ひとりに語りかけるように講義を進めて下さる浜野先生の話に、参加者は明日からの実践に役立てようと熱心に聞き入っていました。

(つづく)